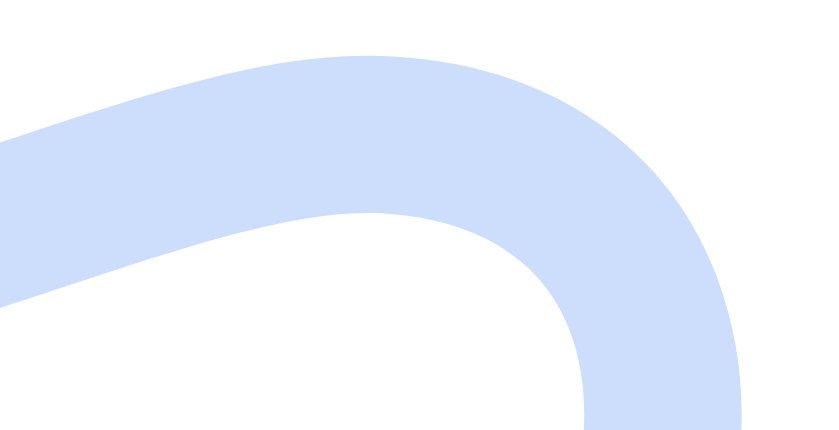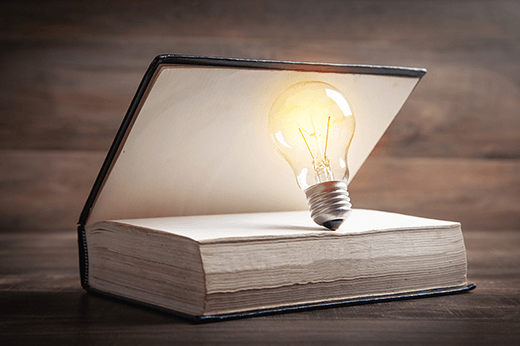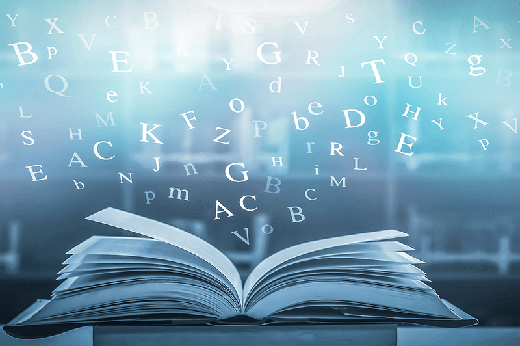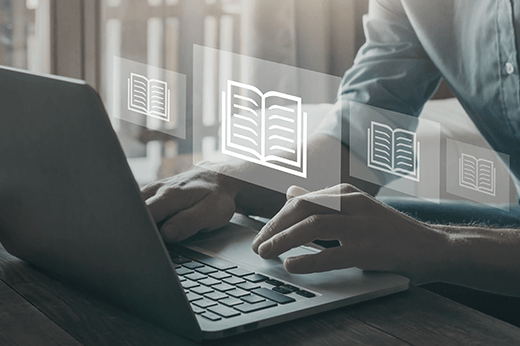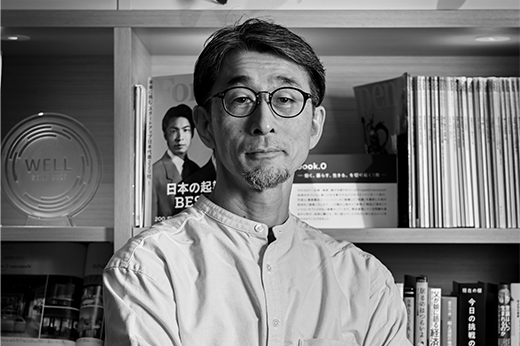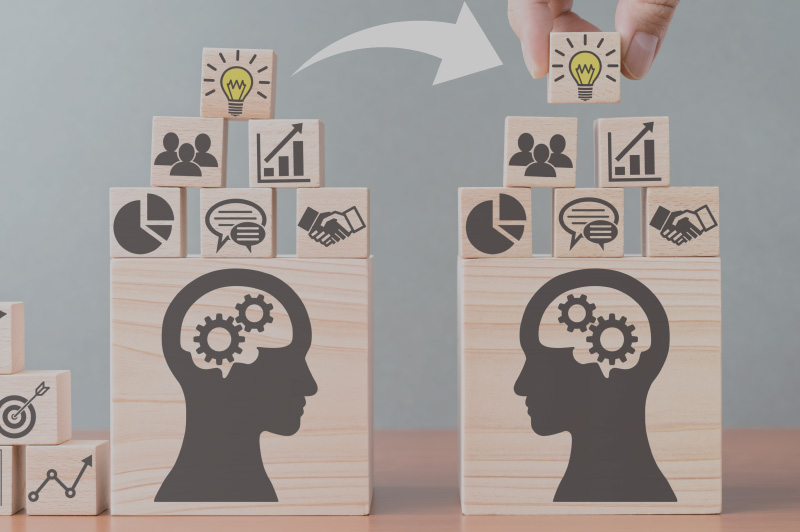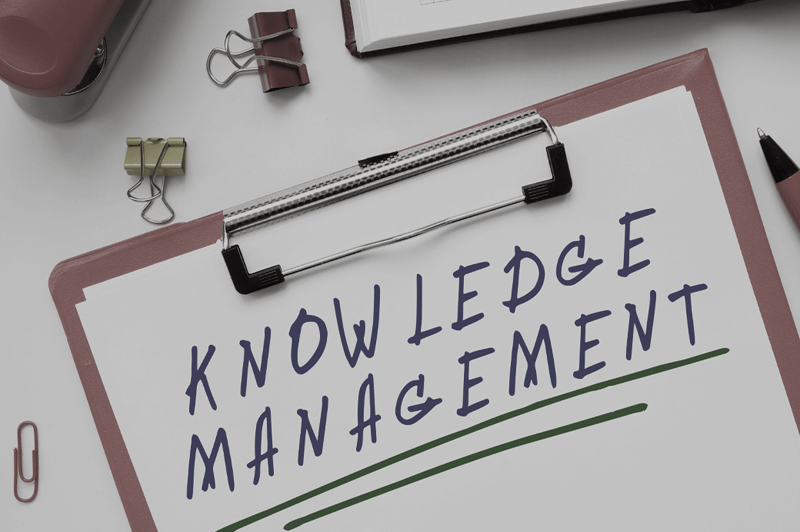SECIモデルとは?
ナレッジマネジメントの基礎的な考え方
- 人材活用
- ナレッジマネジメント

SECI(セキ)モデルとは、個人が持っている暗黙知を形式知として組織全体で共有し、新たな知識を生み出して経営に活かすナレッジマネジメントの理論のひとつです。本コラムではSECIモデルの概要について解説します。「ナレッジマネジメントを調べるとSECIモデルという言葉を頻繁に目にするが、そもそもSECIモデルが何なのか基礎的なことがわからない」という方は、ぜひ参考にしてください。
SECIモデルとは

SECI(セキ)モデルとは、個人が持つ知識や経験などの暗黙知を形式知に変換したうえで、組織全体で共有し、それらを組み合わせることでまた新たな知識を生み出すフレームワークのことで、経営学者の野中郁次郎氏が提唱したナレッジマネジメントの基礎理論です。
SECIモデルは、「共同化(Socialization)」、「表出化(Externalization)」、「連結化(Combination)」、「内面化(Internalization)」の4つのプロセスから成り立っており、これらの頭文字を取ってSECIと名付けられました。このプロセスについては後述いたします。
「暗黙知」と「形式知」とは?
暗黙知は、個人の感覚や経験に基づいた知識やスキルのことで、勘やセンス、コツなども含まれ、周囲に言葉で伝えるのが難しいものを指します。特定の顧客に対応するスキルやこれまでの経験で磨かれたデザイナーのセンスなどが該当します。
一方で、形式知とは、暗黙知と反対の意味を持ち、文章や図解、数値などによって、誰でも理解できるような形式で表現された客観的な知識を指します。特定のタスクや問題をどのように解決するかを明確に示したマニュアルや研修資料などが該当します。
>暗黙知と形式知とは?暗黙知を形式知に変換するメリットと手法
「ナレッジマネジメント」とは?
ナレッジマネジメントとは、社員一人一人が持つ経験や知識、ノウハウなどの「ナレッジ」を社内で共有することで、新たな技術革新や生産性向上のために役立たせることを通じて、事業の成功および企業成長を目指す手法です。
つまり、「自社の社員が業務経験で培ってきた知識やスキルといった企業にとって財産であるナレッジを十分に活用し、イノベーション創出をしたい」といった思いからナレッジマネジメントを実施する企業において、そのフレームワークとなるSECIモデルは重要な理論といえます。
SECIモデルの身近な例

SECIモデルをもう少しわかりやすく説明するために、身近な例を挙げてご説明します。
SECIモデルは「社会化」「外部化」「結合」「内部化」の4つのフェーズから成り立っています。
1.料理教室
料理教室では、まず講師が生徒に料理の手順を実際に見せることで社会化が行われます。
次に、生徒が講師から教わった手順を自分の中に落とし込むことで外部化が行われます。
その後、同じ班の他の生徒が持つテクニックや豆知識を取り入れることで結合が行われます。
最後に、家に帰って自分で料理を作ることでその知識を自分のものとする内部化が行われます。
2.サッカーチーム
新しいプレーを学ぶ際に、まずコーチが選手たちにプレーを実演し、選手たちがその技術を理解することで社会化が行われます。
次に、選手たちは自分たちの言葉でプレーを説明し、理解を深めることで外部化が行われます。
その後、チーム内で戦術を実際に試し、改善点を見つけ出すことで結合が行われます。
最後に、選手たちは試合で実際にその戦術を使うことで内部化が行われます。
SECIモデルを構成する4つのプロセス
SECIモデルは、
Socialization(共同化)
Externalization(表出化)
Combination(連結化)
Internalization(内面化)
という4つのプロセスで構成されています。このすべてのプロセスが上手く機能すれば、ベテラン社員の暗黙知をほかの社員も理解できる形式知として共有することができ、全社員のスキルアップにつながると言われています。
Socialization(共同化)
Socialization(共同化)とは、言葉ではなく経験によって、暗黙知を伝えていくやり方です。学ぶべきことはマニュアル化されておらず、先輩社員の仕事を見よう見まねで覚えます。
Externalization(表出化)
Externalization (表出化)とは、Socialization(共同化)によって得た暗黙知を形式知に変換するステップです。経験によって学んだノウハウを言葉や図解で表現し、マニュアルに落とし込むことが該当します。
Combination(連結化)
Combination(連結化)とは、Externalization (表出化)によって変換された形式知を、ほかの形式知と組み合わせるステップです。例えば他部署のマニュアルと比較すれば、より包括的なマニュアルが作成できます。
Internalization (内面化)
Internalization(内面化)とは、Externalization (表出化)とCombination(連結化)の過程を経てまとまった形式知が、個人の暗黙知へと変わっていく段階です。マニュアルの内容を実践しているうちに、新たに自分の中に溜まっていく知見は再び最初のステップへと戻り、組織へ浸透していきます。
SECIモデルに必要な4つの「場」と具体的な事例
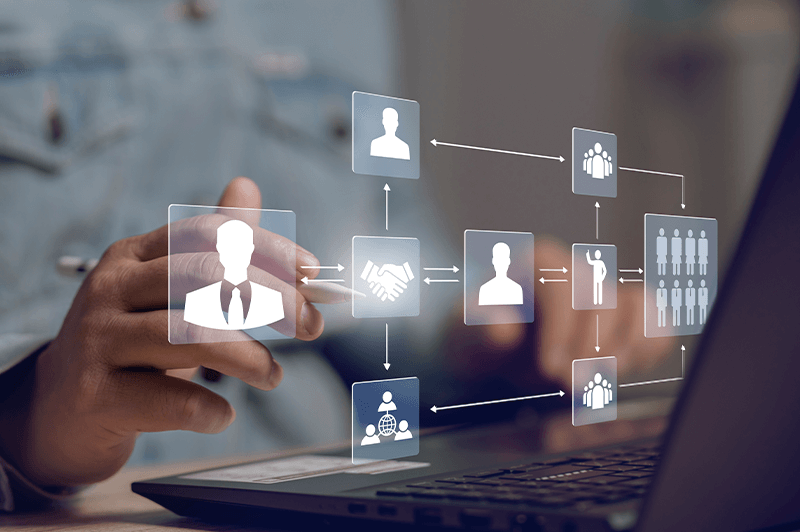
上述の4つのプロセスを行うためには、それぞれのプロセスに適した「場」があるとSECIモデルでは提唱しています。
創発場
対話場
システム場
実践場
の各プロセスにおいて、具体的な例を挙げて解説します。
創発場
創発場とは、共同化プロセスにおいて重要な「他者と知識の交換を行う場」を指します。
先輩社員が若手社員に知識や技術を伝えるOJT(On the Job Training)研修や、手工業の技能の分野で多く見られる徒弟制度といった、一緒に作業して伝えるものもあれば、休憩中の雑談や終業後の食事・飲み会などでの気軽な会話から知識を交換する方法もあります。
創発場の具体例
・休憩室や廊下のすれ違いなどの雑談
・昼食や終業後の飲み会など食事での会話
・社内SNSやチャットルームでの情報交換
対話場
対話場とは、表出化プロセスにおいて重要な「暗黙知を形式知に変換する場」を指します。
表出化のプロセスでは、各自が持つ暗黙知を対話を通じて形式知にしていくため、目的を明確にし、プレゼンテーション、ディスカッション、ブレインストーミングなどによって議論を進めます。客観的で論理的な知識として再編集し、汎用性の高いナレッジになるような場の準備が必要です。
対話場の具体例
・業務上の会議全般
・業務マニュアル/資料作成
・全社/部署横断ミーティング
システム場
システム場とは、連結化プロセスにおいて「形式知と形式知が組み合わさる場」を指します。
各社員が形式知を持ち寄って組み合わせる段階であるため。テキストや図などを共有しながら話し合うことが可能な場が適しています。そのため、オンラインでのミーティングや、ナレッジを共有できるツールとし、ナレッジマネジメントツールの利用などの導入を検討しましょう。
システム場の具体例
・オンラインミーティング
・ナレッジマネジメントツール
・社内コミュニケーションツール
実践場
実践場とは、内面化プロセスにおいて「再び暗黙知に変換される場」を指します。
連結化プロセスによって生まれた新たなアイデアを実践しながら業務を進めることで、勘やコツ、ノウハウといった個人の暗黙知を培っていくフェーズであるため、特定の状況や場所はありません。日々の仕事のすべてが内面化の場といえます。
実践場の具体例
・個人が業務を行う業務空間(オフィスのデスクや作業場など)
SECIモデルの課題
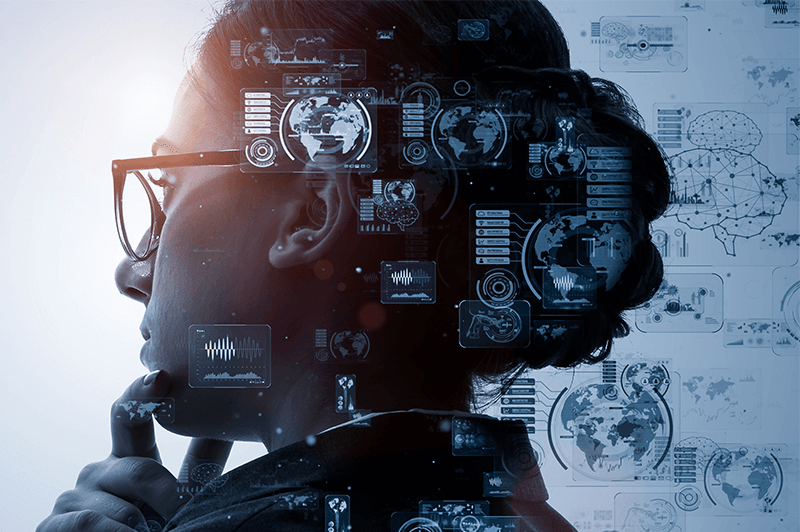
特定の社員が持っている知識や技術を全社的に共有することで、企業力を高めるSECIモデルですが、実際には課題もあります。ここでは主な3つを取り上げてみましょう。
暗黙知から形式知への変換が難しい
暗黙知を形式知に変換するためには、適切な方法でナレッジをデータに変える作業が必要です。文書、図解、動画などを駆使してマニュアルに仕上げるのは、多大な時間や労力がかかってしまうかもしれません。特に複雑な仕事、専門性の高い仕事は形式知に置き換えるのが難しく、途中で社員が投げ出してしまう可能性も考えられます。
自身が持っている知識を形式知化することにメリットを感じない
キャリアのある社員、高度な専門知識や技術を持っている社員が、自身のナレッジを他の社員に共有するメリットが少ないと考えていることは、SECIモデルが機能しない一因です。なぜ自分が時間をかけて習得した内容をシェアする必要があるのかが理解できない、多忙でありナレッジマネジメントは優先したと思えない、といったケースが見受けられます。
反復して獲得する必要がある
情報共有をしてもらったあと、その知識や技術を個人が吸収することに意義があります。それは業務の合間を縫って、個人の裁量で行わなければなりません。高度な内容ほど一度では体得できないので、自分自身に落とし込むには時間がかります。Internalization (内面化)が、最も個人の能力に左右されるステップです。
SECIモデルを実践するためのポイント

上述の課題を踏まえて、SECIモデルを実践していくためのポイントについて解説します。
暗黙知を表出化する工夫
暗黙知を形式知に変えるためには、社員がストレスなく情報を共有・活用できるように導線を用意する必要があります。具体的には、ナレッジを共有する際に使いやすいテンプレートを作成すること。ナレッジを蓄積するときに対応するべきルール、盛り込むべき内容などを整理します。経験がない業務のナレッジルールを決める場合は、経験者へヒアリングします。
継続的な改善と評価
SECIモデルの実践は一度きりではなく、継続的なプロセスです。定期的に実践の成果を評価し、改善点を見つけることが重要です。フィードバックを収集し、モデルの各ステージが効果的に機能しているかを確認します。必要に応じてプロセスを調整し、組織のニーズに合わせて最適化しましょう。
まとめ
既に多くの企業がSECIモデルの活用を試みています。確かにSECIモデルにはまだ課題もありますが、自社の状況を踏まえながら上手く機能させることで、必ず各社員のスキルアップにつながっていきます。
また、Combination(連結化)のフェーズでは、ナレッジマネジメントツールの導入が効果的です。ベテラン社員は自身の知見をシェアすることの意味を理解する。知識をシェアされた社員は学び続ける。もちろん「人」の頑張りが大前提です。その上で効率化を図れるところを見極めつつ、社内のナレッジマネジメントを進めてみてください。
ナレッジマネジメントにおすすめのツールとして、「saguroot」があります。ファイル共有だけではなく、その背景にあるナレッジや人材の交流を目指した設計が特徴です。暗黙知を持つ人材と、若手社員がつながりやすい環境を構築することで、SECIモデルの実践をサポートします。sagurootの詳細は以下の資料よりご覧ください。