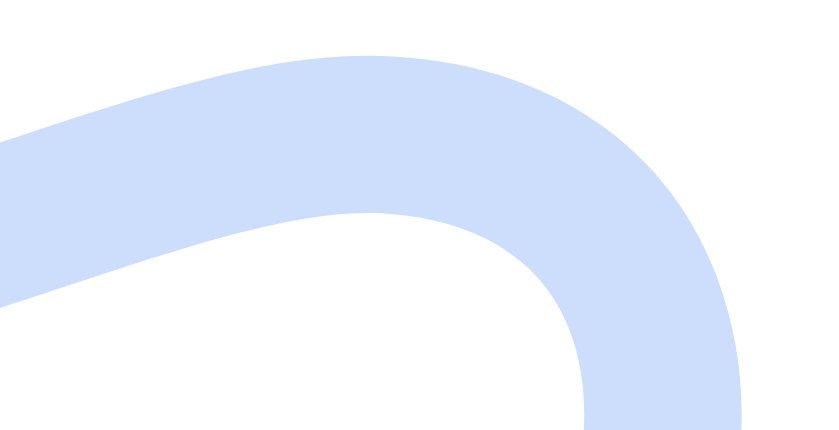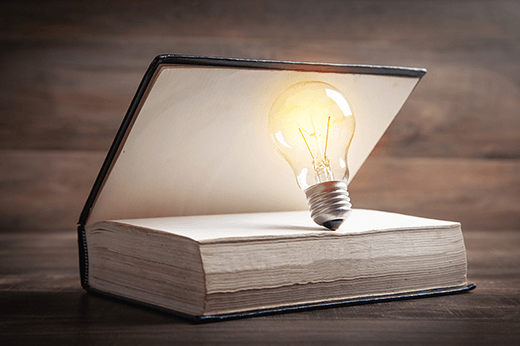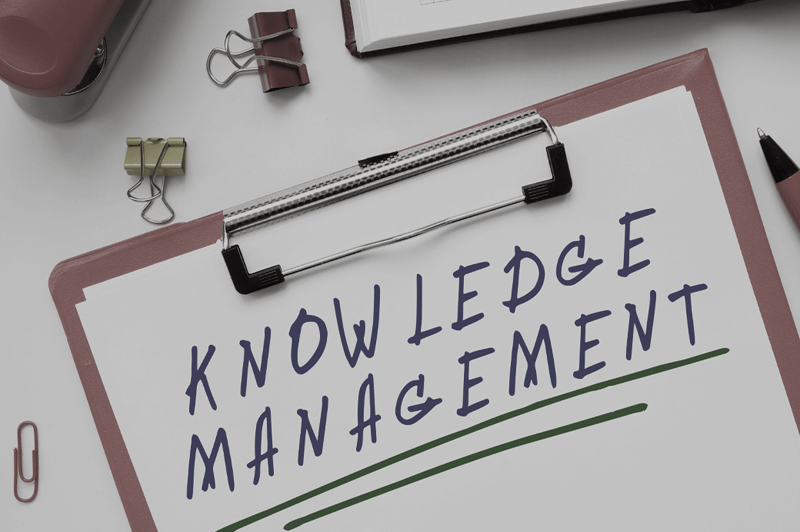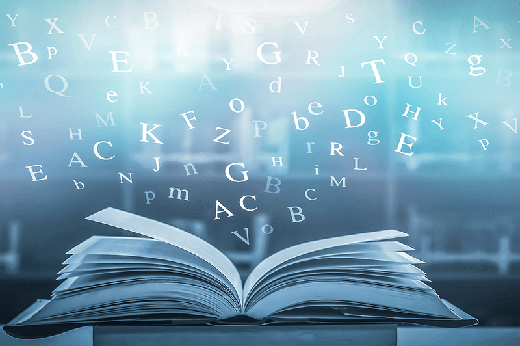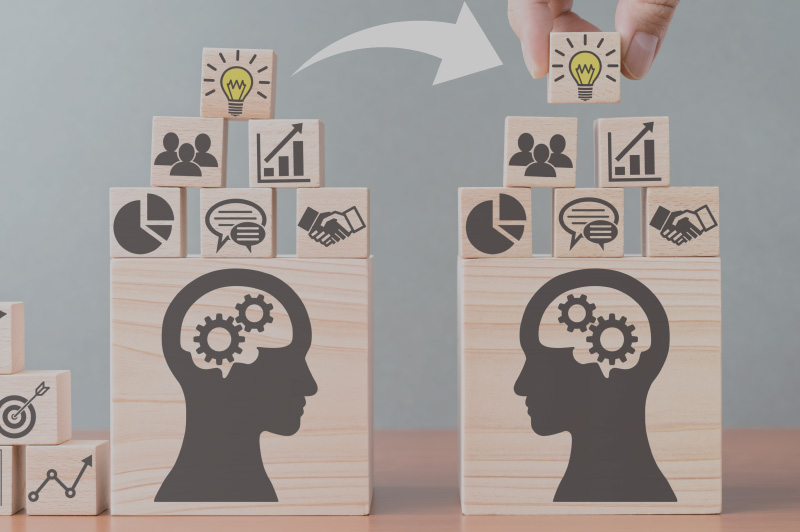ナレッジ共有ツールとは?選び方からおすすめツールまで解説
- ナレッジマネジメント

社内に蓄積されたノウハウや業務知識を活かし、組織全体の生産性を高めるために欠かせないナレッジ共有。しかし、情報が部署ごとに散在していたり、必要な知識にたどり着くのに時間がかかると、せっかくの資産も十分に活用できません。そこで注目されているのが、ナレッジ共有を効率化する「ナレッジ共有ツール」です。本コラムでは、ナレッジ共有の基本から、ツールの主な機能や導入メリット、目的に合った選び方までを解説。自社の情報活用力を高めたい方の参考になればと思います。
ナレッジ共有とは?

ナレッジ共有とは、個人が蓄えてきた知識やノウハウを、チーム内や組織全体で共有することです。ナレッジ共有が上手く行くと、社員のスキルが全体的に底上げされたり、組織としての生産性を高めたりできるようになります。なおナレッジとは単純に用語を解説する辞書のようなものではなく、専門分野における経験や有益なテクニック、問題解決のための実践的な知見も含む概念です。
ナレッジ共有ツールとは?

ナレッジ共有ツールとは、社員が持つ知識や経験、業務のノウハウなどを組織全体で蓄積・共有・活用するためのシステムです。社内Wiki、ナレッジベース、FAQ管理、ドキュメント共有ツールなどが含まれ、情報の作成、分類、検索、更新を簡単に行えるよう設計されています。これにより、情報の属人化を防ぎ、誰でも必要なナレッジにすぐアクセスできる環境が整います。また、過去の成功事例やトラブル対応の記録をもとに、業務の効率化や標準化を推進できる点もメリットです。さらに、チャットやプロジェクト管理ツールと連携することで、日々の業務の中で自然にナレッジが蓄積され、チーム全体の生産性向上にも寄与します。ナレッジ共有ツールは、現代の組織運営において欠かせない存在になっています。
ナレッジ共有ツールの機能

ナレッジマネジメントツールに搭載されている一般的な機能には下記などがあります。
ヘルプデスク(FAQ)
業務中に出てきた質問に対して、社員同士で回答し合える機能がヘルプデスク(FAQ)です。何度も同じ内容の問い合わせが来て、その度に同じ回答をするのが非効率である、カスタマーサービスのオペレーターが不足している、などの状況を改善するのが目的です。
ファイル共有(ドキュメント管理・文書管理)
社員同士でファイルの送受信ができるほか、タグ付けが行えるなど情報を取り出しやすくするための機能です。文書ドキュメントに特化し、検索性に長けているのが特徴で、文書ドキュメントを整理して、必要なときに必要な文書にアクセスできるようにします。
チャット・コメント機能
ナレッジの内容に対して、チャット形式でやりとりができたり、コメントを残せる機能です。疑問点をすぐに質問したり、更新があった際に気軽にフィードバックを送ることができます。単なる一方向の情報共有ではなく、双方向のコミュニケーションを促すことで、ナレッジの活用と定着を後押しします。
ナレッジ共有ツールを導入するメリット

ナレッジマネジメントツールを導入すると、どんな良いことがあるのでしょうか。4つのメリットを洗い出してみました。
ナレッジの属人化防止
ナレッジマネジメントツールは、属人化の解消に有効です。業務進捗の管理やチームのスムーズなコミュニケーションを促すものにはじまり、前述のヘルプデスク(FAQ)や、ファイル共有(ドキュメント管理・文書管理)など属人化の解消に役立つツールは多数あります。適切なツールを選んで、本質的な業務に集中できる環境が整うことで、効率よく属人化の解消が進みます。
ナレッジへのアクセシビリティ向上
アクセシビリティとは、誰もが提供されている情報やサービスを利用できることを指します。ナレッジマネジメントツールの中でも、検索機能に特化したツールを導入すれば、複数のファイルサーバの検索に加えて、Boxなどのクラウドストレージも含めた一括検索が可能で、必要な情報にたどりつくのにかかる時間を大幅に削減でき、アクセシビリティが向上します。
ナレッジを持つ社員を可視化できる
情報源がわからず、何人にもメールしたり電話したりといった経験はないでしょうか?ドキュメントファイルの作成者がわかれば、そのナレッジを持っている社員を特定できます。読めばわかるナレッジももちろんありますが、より深く知りたい場合は直接その社員と話したほうがスムーズかもしれません。情報の共有範囲を広げれば、異なる支店や部門をまたいだ交流も生まれやすいです。
社員のスキルアップが期待できる
ナレッジマネジメントツールによって個々の社員が持っていた技術やノウハウが集約されれば、検索するだけで必要な情報が得られるだけでなく、ベテランスタッフの時間や労力の削減に。質の高いナレッジが行き渡ることで、すべての社員のナレッジ・スキルを底上げできます。また成功事例や失敗事例を分析することで、新しい製品やサービスの開発にもつなげられます。
ナレッジ共有ツールの種類と選び方

ナレッジ共有ツールの種類と選び方を紹介します。
ナレッジ共有ツールの種類
【機能重視型】
社内Wiki型のナレッジ共有ツールは、業務マニュアルや手順書などの文書を体系的に整理・蓄積するのに適しています。ページ階層で情報をまとめやすく、検索機能も充実。直感的に編集できるツールも多く、ITリテラシーが高くなくても扱いやすい点が魅力です。また、コメント機能や更新履歴により、チーム内での共同編集もスムーズ。ルールやナレッジの一元管理をしたい企業には特におすすめです。
【資料管理重視型】
ファイルベース型のツールは、ドキュメント・表計算・スライドなどのファイルをクラウドで保存・共有するタイプです。共同編集やコメント機能があり、リアルタイムでの作業も可能なものが多くあります。アクセス権の管理も細かく設定できるため、部署やプロジェクトごとに柔軟な運用ができます。構造化されたナレッジ管理というより、資料の整理・保存を中心とした用途に向いています。
【コミュニケーション重視型】
チャット連携型は、日々のやりとりの中から生まれるナレッジをリアルタイムに蓄積できるのが特長です。スレッド機能やピン留め、ハッシュタグ機能を使うことができれば、有益な情報を探しやすいです。チャットでの気軽な相談やナレッジ共有がそのまま資産化されるため、Q&A形式の情報ストックにも適しています。スピード感あるやりとりが求められる現場に最適なツールです。
ナレッジ共有ツールの選び方
ナレッジ共有ツールを選ぶ際は、まず「何のために共有するのか」という目的を明確にすることが大切です。たとえば、業務マニュアルの蓄積やナレッジの体系的整理を重視するなら、社内Wiki型のように構造化しやすく、検索性に優れたツールが適しています。一方で、日常的なコミュニケーションから自然にナレッジを生み出したい場合は、チャット連携型が有効です。また、既存の業務フローやツールとの連携、導入コスト、社内のITリテラシーも考慮すべきポイントです。操作が難しいと使われなくなるため、直感的に使えるUIかどうかも大切です。ナレッジが溜まるだけで終わらず、検索・更新・活用がしやすいかも確認しましょう。トライアルを経て、運用ルールや定着度を見ながら導入することをおすすめします。
おすすめのナレッジ共有ツール、saguroot

sagurootは、高度な知的業務を実現するため、社内の「ナレッジ」と「タレント」を見つけることに優れたナレッジマネジメントツールです。AIによるナレッジ検索ファイル名、ファイル内のテキストや画像から検索が可能で、情報を探す時間を大幅に削減。検索結果には、100字程度の資料の要約が表示され、目的と合致した資料かどうかが直感的にわかるのも特徴です。さらに、資料と社員を紐づけるタレント検索機能があるため、機能重視、資料管理重視、コミュニケーション重視と、あらゆるニーズに応えることができます。コストも比較的試しやすい設定なので、ぜひ試してみてください。
まとめ
数名のスタートアップならともかく、ある程度の人数がいる企業では、社内の知識や情報を全社員でシェアするのは困難です。ぜひナレッジ共有ツールを味方につけましょう。そもそも、自分の知識や経験だけに頼って仕事を進めるのは非効率です。社内には、自分では思いもよらないナレッジを持つ社員がたくさんいます。「自分の知見は社員のために、社員の知見は自分のために」。そんな意識を持って、個人の成長と組織の強化を同時に叶える、よいナレッジの循環をつくっていきましょう。
sagurootは、ファイル形式を問わず横断的な一括検索が可能で、ファイル名だけではなく、ファイル内のテキストや画像まで含めて検索できるナレッジマネジメントツール。さらに、任意のジャンル分けと組み合わせることで価値あるファイルを見つけ出すことが可能で、効率的なナレッジ共有をサポートします。