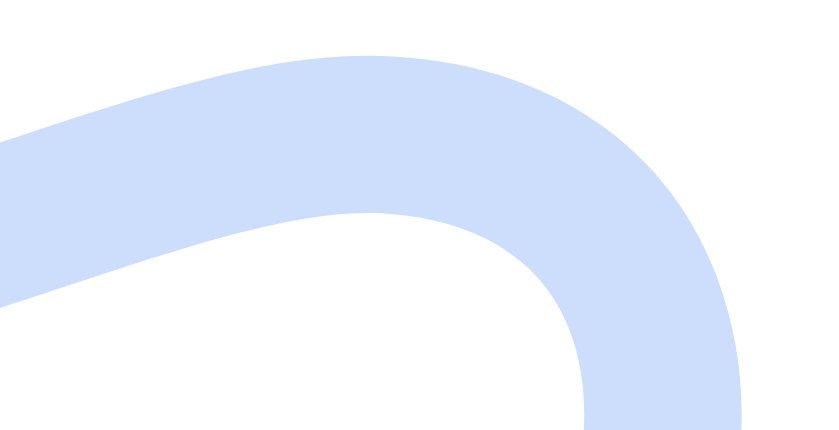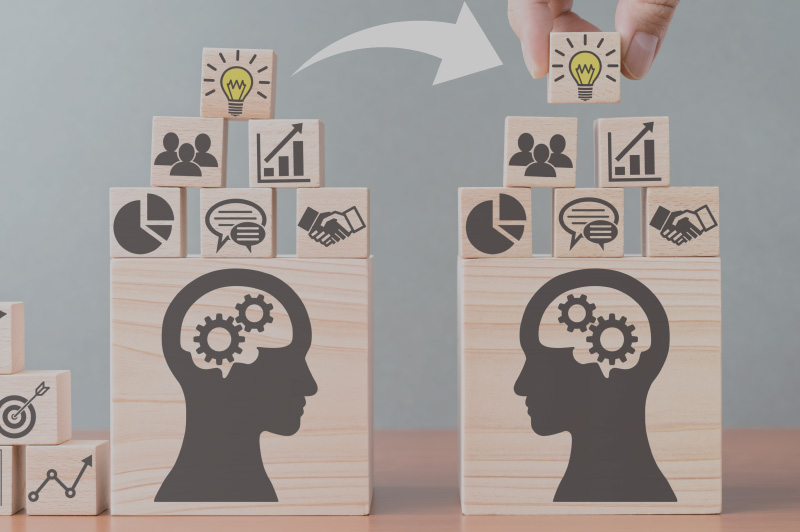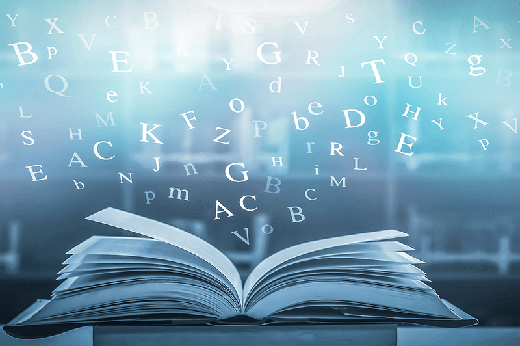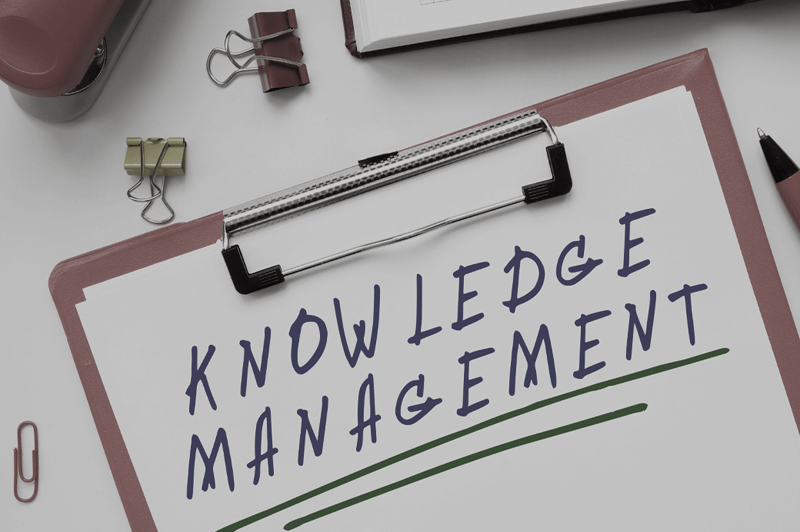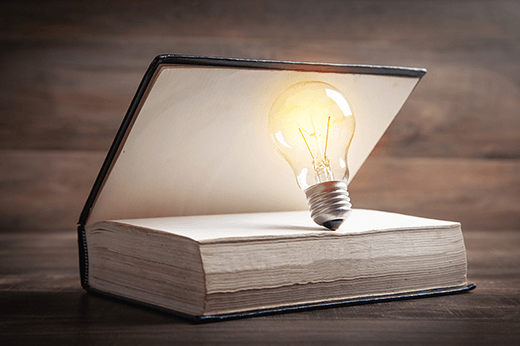ナレッジマネジメントを適切に運用するには?ツール活用や考え方などを解説
- ナレッジマネジメント

組織の知識やノウハウを効果的に活用するための「ナレッジマネジメント」は、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、思うように活用されず、運用が形骸化してしまうケースも少なくありません。その原因には、ツールの選び方や運用ルールの不備、社員の理解不足などさまざまな要素が絡んでいます。本コラムでは、ナレッジマネジメントの基本から、よくある失敗例、そして適切に運用するためのポイントをピックアップ。効果的なツールの選び方についても紹介し、組織の知識活用を成功に導くためのヒントをお伝えします。
ナレッジマネジメントとは?

ナレッジマネジメントとは、知識やノウハウ、成功事例や失敗事例といったナレッジを社内で共有し、企業の成長につなげていく経営手法のこと。言語化が難しい「暗黙知」を、誰もが理解できる「形式知」へと転換し、全社員で活用することがナレッジマネジメントの目的です。社内でナレッジマネジメントがうまく回っていると、業務の効率化や組織内の連携の強化、人材育成の面でも効果を発揮します。
ナレッジマネジメントでよくある失敗例
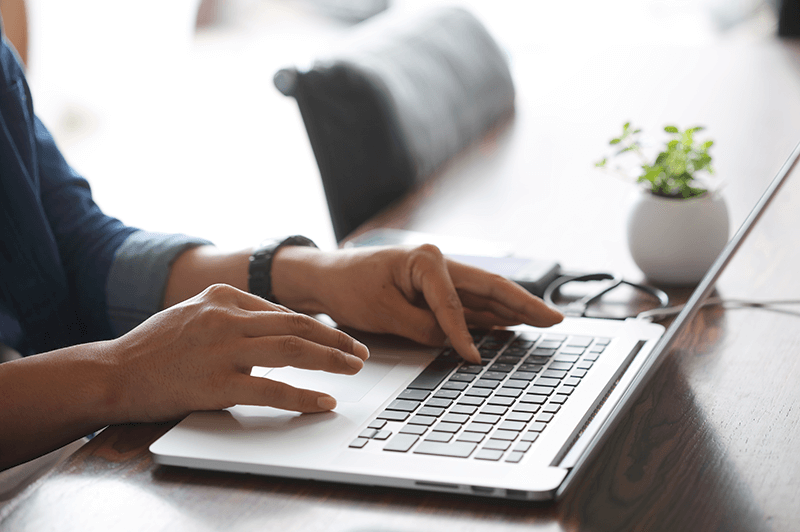
ナレッジマネジメントでよくある失敗例を解説します。
ナレッジが集まらない
ナレッジマネジメントの重要性やメリットが伝わっていなければ、社員の協力を得るのは難しいです。「忙しくてナレッジを共有する時間が作れない」「共有するべきナレッジを持っていないと思っている」なども集まらない原因です。一度集めたとしても、活用をしてみると過不足が出てきますし、時間が経つと使えない内容が出てくるなどで更新も必要になります。
ナレッジが散らばっている
検索性に優れたツールやシステムを導入しても、必要なナレッジが集約されないまま、社内のあちこちに散らばっているというケースも多く見られます。当然登録されていないナレッジは探し出すことができないため、スムーズなナレッジ共有を実現することはできません。ナレッジ検索で必要な情報を探し出せるようにするためにも、社内のナレッジは、集約して一元管理しておくことが重要です。
「データの共有」に留まっている
ナレッジマネジメントが、データの共有レベルに留まってしまっているケースがあります。散在するデータを1箇所に集めて形式を揃え、整理してデータを検索できる状態にするところまでは労力が必要です。それもあってか、データ共有や検索できた段階で安堵してしまい、そこが一旦のゴールとなってしまっていることはよくあります。
ツールの使い方が分からず活用しきれない
初期設定や操作が難しかったり、どこに何を投稿すればいいか不明確だったりすると、利用が定着しません。まずは簡単なマニュアルや使い方のガイドを整え、チームでルールを共有することが大切です。定期的な研修や質問の場を設けるのも効果的です。使い方に慣れれば、情報共有はスムーズになります。
社内でナレッジマネジメントの意識が低い
社内でナレッジマネジメントがなかなか浸透しないという課題です。ナレッジマネジメントは、経営層にとってはメリットが大きくても、社員一人一人にとってはメリットが感じにくいことが原因と考えられます。自分の知識や経験をシェアしたくないと考える人もいます。
ナレッジマネジメントで適切な運用をするためのポイント

ナレッジマネジメントを適切に運用するためには、どのようなポイントがあるのでしょうか。
ナレッジマネジメントの目的を明確化する
ナレッジマネジメントを成功させるには、まず「なぜ共有するのか」「どんな成果を目指すのか」という目的の明確化が欠かせません。たとえば、「業務の属人化を防ぐ」「新人教育を効率化する」「顧客対応の質を均一化する」など、組織ごとの課題に応じてゴールを定めることで、共有すべき情報や活用方法が明確になります。目的が曖昧なままだと、ただ情報をため込むだけになりがちで、現場で活かされません。まずは共通認識として目的を明確に定義しましょう。
共有するナレッジを選別・整理する
ナレッジは全てを記録・共有すればいいというものではなく、目的や利用頻度に応じて選別・整理することが重要です。業務手順やFAQ、成功・失敗事例など、現場で繰り返し参照される情報は優先的に共有すべきです。また、情報の重複や古い内容を残しておくと混乱のもとになるため、定期的な見直しも必要です。整理されたナレッジは検索性や活用度が高まり、業務の効率化に直結します。質の高いナレッジを選び、使いやすく整備する意識が求められます。
ナレッジの蓄積~共有~活用を実行しやすい環境を整備する
ナレッジマネジメントは「ためる・見せる・使う」の循環が回ってこそ機能します。そのためには、誰もが気軽にナレッジを投稿・検索・活用できる環境整備が欠かせません。投稿のハードルを下げるために入力フォーマットを統一したり、検索しやすいタグやカテゴリを設けたり、活用事例を紹介することで「使われる文化」を育てることが大切です。また、業務と並行して運用できるよう、時間確保や評価制度にナレッジ活動を組み込むと継続性が高まります。
ナレッジマネジメントに適したツールを導入する
ナレッジを組織内で活用するには、目的や運用体制に合ったツールの選定がカギです。たとえば、社内Wikiやチャットツール、ナレッジ専用のプラットフォームなど、使いやすさ・検索性・投稿のしやすさなどを比較し、現場が自然に使えるものを選びましょう。また、ツール導入だけで満足せず、活用のルール整備や定期的なメンテナンスも不可欠です。さらに、利用状況を分析し、改善につなげる仕組みがあると、ツールを活かした運用が継続的に可能になります。
ナレッジマネジメントツールの選び方

上記を踏まえたうえで、ナレッジマネジメントツールの選定ポイントをまとめました。
過不足なく機能があるか
基本的な機能です。導入の目的や自社の課題に合わせて、必要なものを洗い出しましょう。
・ファイル共有:文書や画像などのファイルを一元管理し共有する機能
・情報検索:キーワードやタグなどでファイル内の情報を高速に検索する機能
・コメント&フィードバック:ファイルにコメントやフィードバックを付ける機能
・バージョン管理:ファイルの編集履歴を確認する機能
・アクセス権限管理:データの閲覧・編集・削除などの権限を設定する機能
操作性が良いか
ツール選定時に気を遣いたいのが操作性です。多機能かつ高性能なナレッジマネジメントツールでも、もし操作性が悪くて使いづらければ、結局使われないものになります。社員のITリテラシーには差があるのが現実なので、なるべく誰にでも簡単に操作できるものを選ぶようにしましょう。ほとんどのツールで無料トライアルが可能ですので、実際に使って操作性をしっかりと確認します。
人材別に検索できるか
ナレッジマネジメントの本質は、実はデータではなく人。常にナレッジを取りに行ける環境であることと同時に、社内のさまざまな強みを持ったエキスパートを発掘できる仕組みがあれば、業務効率も組織の成長も大きくアップします。ファイルとその担当者の情報を可視化し、社内コミュニケーションを活性化することも重要なポイントです。
まとめ
ナレッジマネジメントは、単に情報をためる仕組みではなく、「知っている人の知恵」を「知らない人の力」に変えるための取り組みです。ツールを入れただけで終わりではなく、目的の明確化、共有ナレッジの選別、環境整備、そして適したツール選びまで含めて、ようやく活用のスタートラインに立てます。重要なのは、現場で“使われる”こと。業務の中に自然とナレッジが入り込み、循環するような仕組みこそが、持続可能なナレッジ運用のカギです。
働き方が大きく変わった今、「知っている人にちょっと聞く」が難しくなりました。リモートワークが当たり前になり、世代も職種もバラバラなチームが増える中で、「誰が何を知っているのか分からない」「どこに何の資料があるのか探しきれない」と感じる場面は、誰にでもあるはずです。そこで注目されているのが、ナレッジマネジメント。単に情報を集める仕組みではなく、知っている人の知恵を、社員みんなの力に変える取り組みです。ツールを入れただけで終わりではなく、何を共有するのか、実際に活用されているか。そのすべてをデザインして初めて、ナレッジは組織の中で循環し始めます。
sagurootは保存しているファイル形式を問わずに資料を一括で検索でき、さらにファイル内のテキストや画像まで含めて検索が可能。分類による絞り込み、一目でわかるサムネイル、AIで生成される資料の要約など、高い検索性が特長です。また、資料と担当者情報を紐づけることにより、知見を持つ人材を可視化することで、“活きたナレッジマネジメント”を実現します。