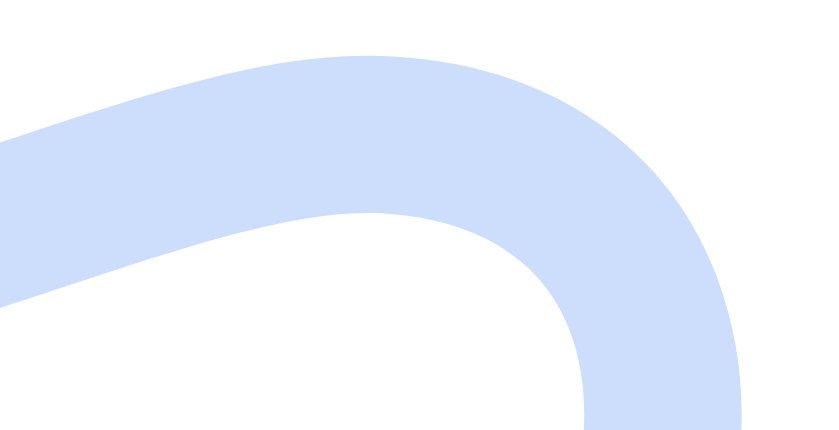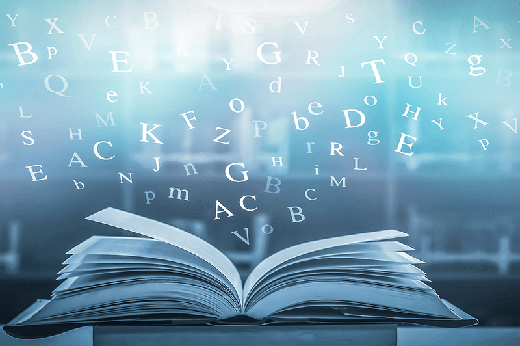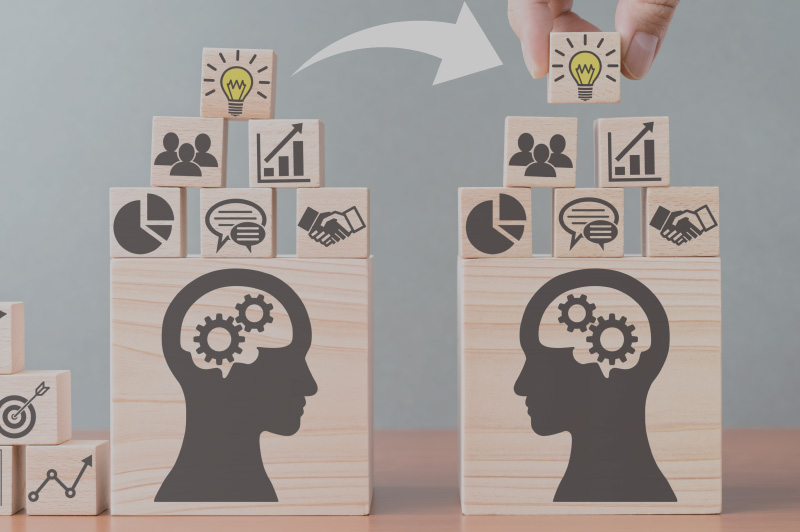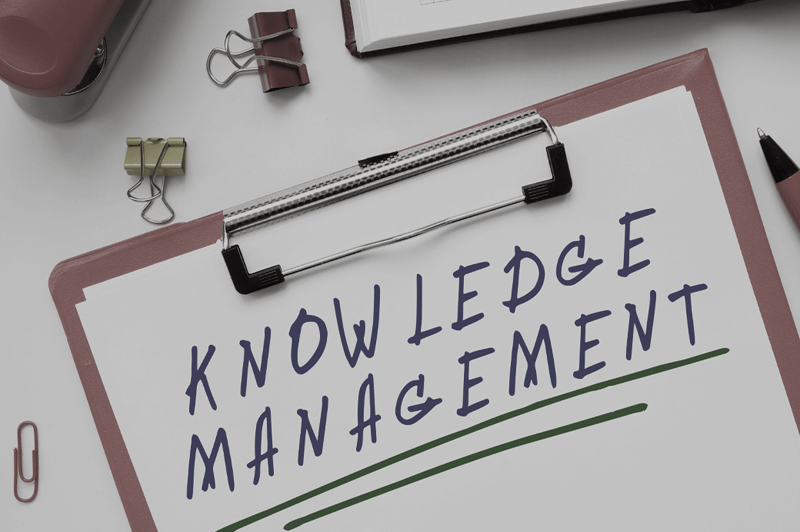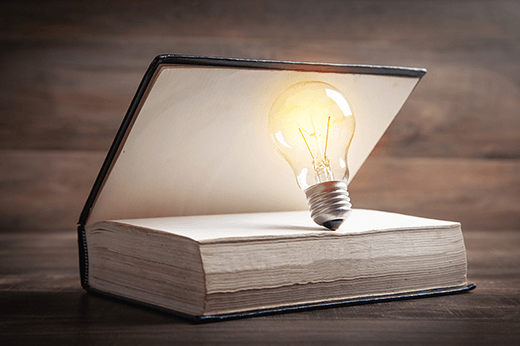ナレッジトランスファーとは?具体的な方法・進め方からメリットまで解説
- ナレッジマネジメント

ベテラン社員の異動や退職、プロジェクトの引き継ぎ——こうした場面で、これまで組織に蓄積されてきた知識やノウハウを次の人へ確実に伝えることは、企業の競争力を維持・強化するうえで欠かせません。そこで重要になるのが「ナレッジトランスファー(知識伝達)」です。ナレッジトランスファーは単なる情報共有ではなく、経験や判断基準といった暗黙知も含めて、業務に活かせる形で伝えることが求められます。本コラムでは、ナレッジトランスファーの基本から具体的な進め方、実施時の注意点や役立つツールまでを網羅的に解説します。
ナレッジトランスファーとは?

ナレッジトランスファー(Knowledge Transfer)とは、ある個人や組織が持つ知識・経験・ノウハウを、別の個人やチーム、部署へと移転・共有するプロセスのこと。業務の属人化を防ぎ、組織全体の知識資産を有効に活用するための重要な施策です。ナレッジトランスファーは、マニュアルの整備やドキュメント共有、定期的なミーティング、ベテラン社員による指導、OJTなどを通じて行われます。また、ナレッジトランスファーの対象には意思決定の背景や判断基準といった“暗黙知”も含まれます。情報の伝達にとどまらず、状況に応じた知識の活用や思考も含めて伝える点が特徴です。
一方で、スキルトランスファー(Skill Transfer)は、特定の技術や操作など、比較的具体的で測定可能な能力を伝えることを意味します。ナレッジトランスファーが「考え方」や「知恵」などの暗黙知を重視するのに対し、スキルトランスファーは「手の動かし方」や「やり方」など具体的なポイントにフォーカスする点が異なります。組織力の強化には双方のバランスが欠かせません。
ナレッジトランスファーのメリット

次に、ナレッジトランスファーを実行するメリットを紹介します。
ナレッジの蓄積により属人化防止
ナレッジトランスファーを行うことで、個人が持つノウハウや経験をチームや組織全体で共有できます。これにより、その人にしかわからない属人化の状態を防ぐことが可能になります。また、業務の進め方や判断の背景が見える化されることで、急な異動や退職があっても、業務がストップせずにスムーズに引き継がれます。誰が担当しても一定の品質を保てるようになり、組織としての安定性が向上。結果として、リスクを分散しながら、人材の入れ替わりにも柔軟に対応できる体制が整います。
業務効率の向上
ナレッジトランスファーを通じて、過去の成功事例や失敗の教訓、効率的な業務の進め方が共有されれば、同じミスを繰り返したり、非効率な手順に悩んだりすることが減ります。経験の浅いメンバーも、蓄積された知見を活かしてスムーズに業務を進められるようになり、教育にかかる時間やコストも削減できます。ベテランと若手の間で知識が循環することで、人材育成のスピードもアップ。結果として、チーム全体のパフォーマンスが底上げされ、組織全体の業務効率が大きく向上します。
イノベーションの促進により企業競争力向上
ナレッジトランスファーが活発な組織では、多様な視点や経験が交わることで、新しいアイデアや改善提案が自然と生まれやすくなります。個々の知識やノウハウが組み合わさることで、従来の枠を超えた発想が生まれ、イノベーションの土台が築かれていきます。また、情報の流れがスムーズになれば、意思決定のスピードも速くなるため、変化の激しい市場環境にも柔軟に対応できます。こうした知的生産性の向上は、組織の持続的な成長を支え、企業の競争力を大きく高める原動力となるのです。
ナレッジトランスファーの方法・進め方

ナレッジトランスファーの進め方について、以下5種類を解説します。
戦略移転
戦略移転とは、企業の中長期的なビジョンや経営方針、ビジネスモデルなど、企業全体の方向性に関わるナレッジを共有・移転するプロセスです。トップマネジメントから現場まで一貫性を持たせるために行われ、M&A後の統合や新規事業展開の際などに重要となります。成功の鍵は、経営陣の強いコミットメントと、全社的な共通認識の醸成です。抽象度が高いため、言語化とビジョンの浸透に向けたストーリーテリングや定期的な対話が求められます。
連続移転
連続移転とは、ある部署やプロジェクトチームで得られた知見や成功事例を、同様の業務を行う別の部署やチームへと段階的に移転していく手法です。たとえば、店舗運営のノウハウを他店舗に展開するケースが該当します。最初の成功例をベースに、ナレッジをテンプレート化・マニュアル化し、トレーニングやOJTなどを通じて横展開していきます。移転元と移転先の状況を比較し、調整しながら移転することが成果につながります。
近接移転
近接移転とは、ほぼ同じ状況や条件下にあるチーム・拠点間でナレッジを共有・活用する方法です。たとえば、同じ製品ラインを持つ工場間での業務改善ノウハウの移転などが挙げられます。業務内容や組織文化が似ているため、ナレッジの適応や定着がしやすいのが特徴です。移転にあたっては、具体的な手順書や成功事例の共有、担当者同士の直接的な交流が効果的です。移転元と移転先の信頼関係を築くこともスムーズな導入には不可欠です。
遠隔移転
遠隔移転とは、業務内容や組織構造、文化が大きく異なる部門や拠点間でナレッジを移転する方法です。たとえば、開発部門の知見を営業部門に応用するケースなどが当てはまります。前提条件が異なるため、単純な知識のコピーでは効果が出にくく、再構築や再解釈が必要です。異なる視点や専門性を持つ相手に向けた翻訳力や、共通言語の整備がカギとなります。多様なメンバーとの対話を重ねることで、新しい価値創出にもつながる可能性があります。
専門知移転
専門知移転とは、特定分野に精通したエキスパートの知識や経験を、他のメンバーや組織に共有・伝承する取り組みです。技術職や研究職、熟練職人の技能継承などが代表例です。暗黙知が多いためマニュアル化が難しく、対話や実地訓練、メンタリングなど、時間をかけた関わりが必要です。近年では、ナレッジベースの構築や、動画・VRを活用した可視化も進んでいます。継続的な学習の場や、知見を引き出す仕組み作りが成功の鍵です。
ナレッジトランスファーを進める際のポイントや注意点

ナレッジトランスファーを推進する際の成功要素や注意点を、3つの観点から解説します。
主導者の決定とリーダーシップ
ナレッジトランスファーを円滑に進めるには、誰が主導するのかを明確にすることが重要です。リーダーは、どの知識を共有するかの選定から、スケジュール管理、関係者の巻き込みまで、全体の舵取り役を担います。現場の信頼を得ている人物が担当すれば、形式だけにとどまらない「活きた知識」の共有が実現しやすくなります。さらに、経営層の後押しがあれば、プロジェクトの優先度も上がり、組織としての推進力が強まります。トップダウンとボトムアップの両面をバランスよく活かしたリーダーシップが求められます。
ナレッジトランスファーに適した環境づくり
ナレッジトランスファーを機能させるには、ツールや仕組みだけでなく、話しやすい雰囲気や信頼関係といったソフト面の整備も欠かせません。心理的安全性が確保されていない職場では、「知らない」と言えなかったり、失敗や経験をオープンに話しづらくなってしまいます。また、形式知だけでなく、暗黙知を引き出すためには、雑談や対話、共創の場を設けることも大切です。ナレッジがただの情報で終わらず、実際の業務に活かされるためにも、「誰でもアクセスしやすい」「気軽に試して改善できる」環境づくりを意識しましょう。
必要なコストの算出
ナレッジトランスファーには、人件費やツール導入費、教育研修費などの目に見えるコストだけでなく、時間や関係者の労力といった目に見えにくいコストもかかります。そのため、計画の初期段階で、伝えるべき知識の価値と、それに伴うコストをしっかり比較検討することが重要です。短期的な成果だけでなく、長期的にどれだけ業務効率や組織力向上に寄与するかを見極め、費用対効果を明確にしておきましょう。コストを過小評価すると、プロジェクトが途中で頓挫するリスクもあります。
ナレッジトランスファーにおすすめのツール

社内に散在するナレッジを蓄積・検索・共有できるsagurootは、属人化しやすい業務ノウハウや暗黙知の可視化を支援するナレッジマネジメントツール。ナレッジトランスファーをスムーズに進めるうえでも、強力なサポート役となります。特に役立つのが、「誰が・どんな知識を持っているか」を可視化できる機能。必要な知見を持つ社員にすばやくアクセスできるため、情報の探索にかかる時間が大幅に短縮されます。また、ナレッジの投稿や評価が簡単にできる仕組みもあり、知識の共有が継続的に活性化されるのも魅力です。ナレッジの見える化と共有を促進し、組織の知をつなげる基盤として、sagurootはナレッジトランスファーの力強い味方になります。
まとめ
ナレッジトランスファーという言葉は耳慣れなくても、実は多くの組織で、何気なく行われてきたことかもしれません。今回は、戦略移転・連続移転・近接移転・遠隔移転・専門知移転といった代表的な分類をあらためて整理したので、自社の取り組みを見直すヒントとして、ぜひ参考にしてみてください。ナレッジトランスファーの精度が高まれば、業務に不可欠な知識やノウハウが、次の世代へと受け継がれ、組織の成長や企業の発展にもつながります。専門ツールも活用しながら、組織の知を未来へつないでいきましょう。
sagurootは、ファイル形式を問わず横断的な一括検索が可能で、ファイル名だけではなく、ファイル内のテキストや画像まで含めて検索できるナレッジマネジメントツール。さらに、任意のジャンル分けと組み合わせることで価値あるファイルを見つけ出すことが可能で、効率的なナレッジ共有をサポートします。