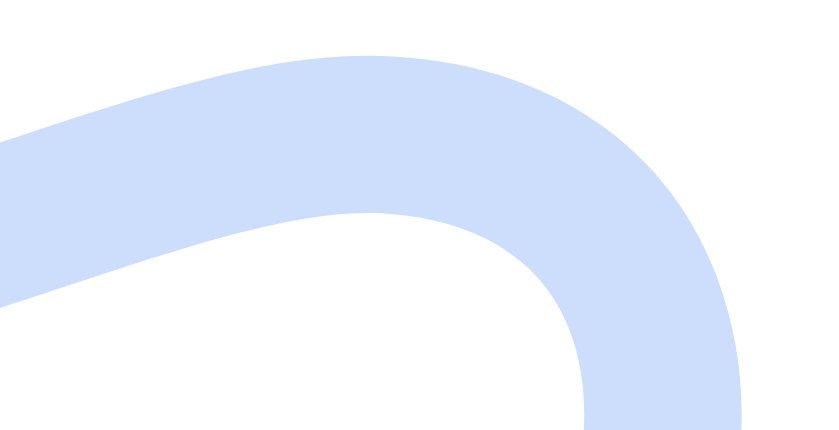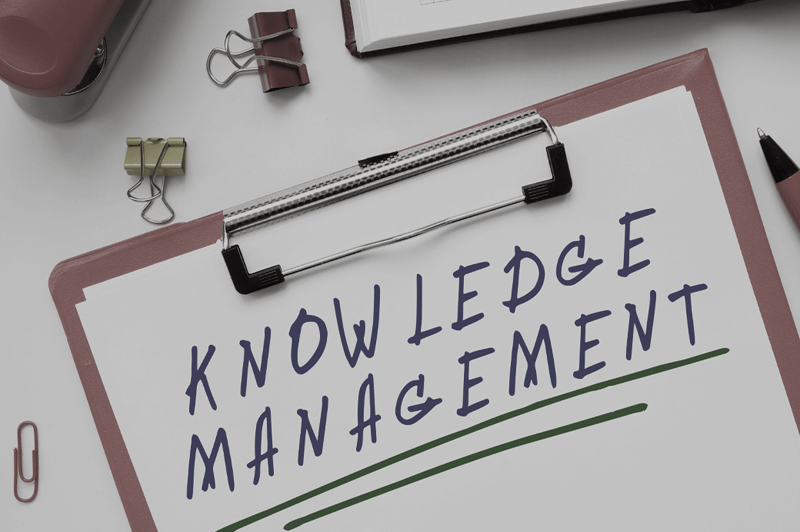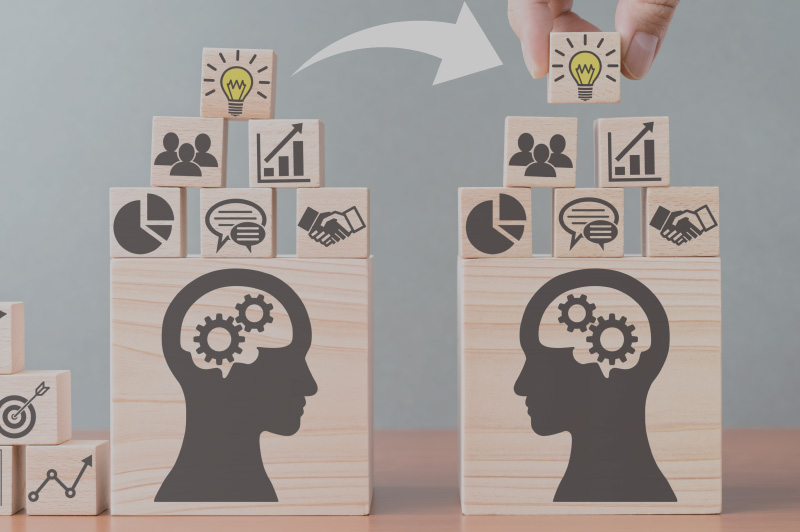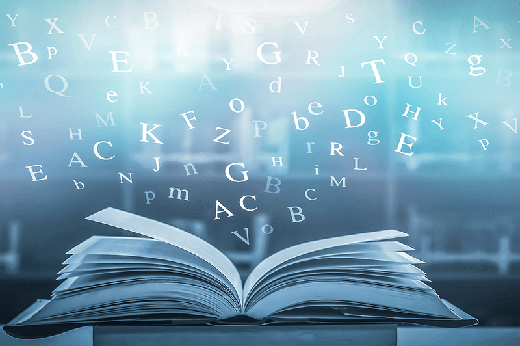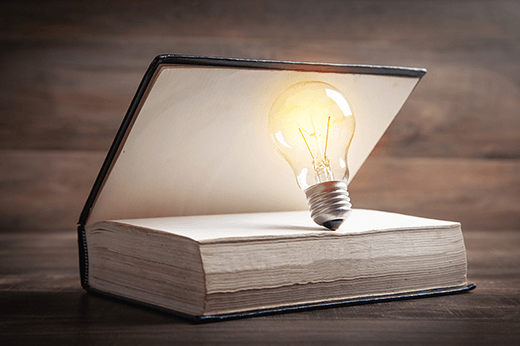有効的なナレッジのまとめ方とは?注意点を踏まえて適切な対策を
- ナレッジマネジメント

業務の属人化を防ぎ、組織の生産性を高めるうえで欠かせないのが「ナレッジの共有」です。しかし、せっかく情報をまとめても「どこに何があるか分からない」「更新されずに古いまま」など、うまく活用されないケースもあります。ナレッジは、ただ蓄積すればよいわけではなく、誰もが使いやすく、更新しやすい形でまとめる工夫が必要です。本コラムでは、ナレッジの効果的なまとめ方を中心に、よくある失敗の原因やその対策、おすすめのツールまでをご紹介。チームや組織の情報資産を活かすためのヒントをお届けします。
ナレッジのまとめ方

まず代表的なナレッジのまとめ方を3種類ご紹介します。
社内Wikiを構築する
社内Wikiとは、社内のナレッジや業務マニュアル、ルールなどをWeb上にまとめ、誰もがアクセス・編集できるようにした情報共有の仕組みです。部署ごとやプロジェクトごとに知識を整理して残しておくことで、情報の属人化を防ぎ、業務の効率化や引き継ぎの円滑化につながります。また長期にわたって使用し、ナレッジの蓄積とブラッシュアップを繰り返すことで、組織の知的資産となります。検索機能やリンクを使えば、情報を横断的に調べられるのも便利なポイント。Wikiツールは多種多様な選択肢があるので、導入のしやすさや、使い勝手の良さをポイントに検討をしてみてください。また構築時には、誰がどのような情報を投稿するか、更新のルールを定めることが肝です。形だけのWikiで終わらせないためにも、実際に使われ続ける運用体制を整えましょう。
FAQシステムを構築、もしくは導入する
FAQ(Frequently Asked Questions)システムとは、よくある質問とその回答をあらかじめ整理し、誰でも簡単に参照できるようにする仕組みです。たとえば、問い合わせが多い部署などでは、同じような質問に何度も答える手間をぐっと減らせますし、ユーザーや社員が自分で調べて解決できる環境をつくることで、全体の業務効率もアップします。またFAQは、社外向けだけでなく、社内向けに使うのもおすすめ。新人研修や業務手順の確認にも役立ちます。構築にあたっては、過去の問い合わせや、業務上のつまずきやすいポイントを洗い出して、ジャンルごとに整理すると見やすくなります。運用面では、定期的な内容の見直しや、検索性を高める工夫も不可欠。専用ツールを活用することで、使いやすいUIと高精度の検索機能を実現できます。
ナレッジマネジメントツールを導入する
ナレッジマネジメントツールとは、社員一人ひとりがもつ知識や経験を社内に共有させるためのツールのこと。チャット、メール、ドキュメント、タスクなど、日常的な業務の中に散在する情報を一元化し、必要なときにすぐにアクセスできる環境をつくることができます。現在は数多くのツールがあり、既存のツールと連携できるタイプもあるので、組織の規模や目的に応じて選びましょう。タグ付けや検索機能が強力なツールは日々の業務フローと相性がよく、活用の幅が広がります。また導入時には、どの情報をどのように管理するかというルール設計が重要です。情報の投稿を促す文化づくりや、運用メンバーによるコンテンツのメンテナンスなど、ナレッジを資産として活かすには、ツール以上に組織内での使われ方が問われます。
ナレッジのまとめ方で失敗してしまう原因

ナレッジをまとめる際に、うまくいかないパターンと原因を説明します。
ナレッジが集まらない
ナレッジが集まらない主な原因は、「誰が、どんな情報を、どのようにまとめればいいか」が明確でないことです。担当者任せになっていたり、投稿の基準やフォーマットが曖昧だったりすると、「面倒くさそう」「自分には関係ない」と感じられて、集まらない状態になりがちです。また、「共有してもメリットがない」と考えている場合や、忙しさを理由に後回しになることもよくあります。まずはナレッジを投稿する意義を共有し、手軽に書ける仕組みやテンプレートを用意することが重要です。投稿者へのフィードバックや感謝を可視化する工夫も効果的です。
ナレッジが検索しづらい
ナレッジを蓄積しても、必要なときに見つからなければ意味がありません。検索しづらい原因には、タイトルが不明瞭、タグやカテゴリ分けが機能していない、ファイル形式がバラバラ、検索機能自体が弱いといった点があります。また、文書内の言葉遣いや表現が統一されていないことも、検索性を下げる要因です。これを防ぐには、検索に強いツールを選ぶことが有効です。投稿時のガイドラインを設けるとともに、ナレッジの分類やキーワードの最適化など、見つけやすさを意識した工夫が必要です。
ナレッジが更新されていない
一度まとめたナレッジがそのまま放置され、古い情報になってしまうことはよくあります。原因は、更新の責任者が不明瞭だったり、更新のタイミングや基準が決まっていなかったりする点にあります。特に、システムや業務内容が頻繁に変わる現場では、古い情報がむしろ混乱を招くこともあります。対策としては、「定期的な見直し日を設定する」「更新履歴を残す」「誰が管理者か明確にする」など、運用面のルールを整備することです。また、気づいた点を社員がコメントできる仕組みも有効な対応策です。
ナレッジのまとめ方で上手くいくための対策やポイント

上述した失敗の原因を踏まえながら、具体的な対応策を押さえておきましょう。
ナレッジ共有の目的を明確化する
ナレッジ共有の第一歩は、「なぜそれを行うのか」という目的を明確にすることです。目的が曖昧なままだと、関係者のモチベーションも上がらず、ナレッジは集まりません。「属人化の解消」「業務の効率化」「新人教育の質向上」など、現場の課題に根差した具体的な目的を設定しましょう。また、目的が共有されていれば、必要な情報の方向性も定まり、「何をどこまでまとめればよいのか」といった迷いも減るはずです。目的を関係者全員と共有し、ナレッジを集める意義を理解してもらうことで協力体制が生まれ、継続的な運用にもつながります。
共有するナレッジの基準を作る
「何をナレッジとしてまとめるか」が決まっていなければ、重要な情報が漏れたり、逆に重複やノイズが増えるなどして検索性が下がってしまいます。そのため、ナレッジ化する情報の基準をあらかじめ定めておくことが必要です。「属人的になっている作業」「問い合わせが多い項目」「週に1回以上発生する業務」など、整理・蓄積する優先度や範囲を明文化しましょう。また、フォーマットやテンプレートを用意すると、情報の粒度や構成にばらつきがなくなりわかりやすくなります。基準が明確であれば、誰もが迷わず投稿・活用できる仕組みが整います。
ナレッジの蓄積~共有~活用を実行しやすい環境を整備する
どんなに良い情報があっても、それが活用されなければ意味がありません。そのためには、「誰でもアクセスできる」「検索しやすい」「更新しやすい」環境の整備が不可欠です。例えば、タグ付けやカテゴリー分けを工夫することで検索性を高めたり、既存のツールと連携できるものを選ぶことで日常の業務フローに自然と組み込めます。また、更新頻度の低いナレッジを洗い出す仕組みや、定期的なレビューのルールを設けることで、情報の鮮度も保てます。ナレッジをシェアする人、使う人、双方にとってメリットあるものにして活用を促進しましょう。
ナレッジをまとめる際におすすめのツール

ナレッジをまとめる際におすすめのツールとして、sagurootをご紹介します。sagurootは、社内の「ナレッジ」と「タレント」を見つけることに優れたナレッジマネジメントツール。高度な知的業務を実現する点が注目されています。最近ではオンラインストレージ、チャットツールの導入拡大により、誰もが情報共有を手軽にできるようになりました。一方で、研究開発や新規事業、企画業務などでは、膨大な情報の中から目的の情報を探し出す手間がかかる現実もあります。また、情報に知見がある人材へ、直接アプローチもしたいというニーズも強くあります。資料と社員を紐づけるsagurootのタレント検索機能は、速やかに情報を検索できるだけではなく、データ共有をきっかけにした社内のコミュニケーションを後押し。新たな価値を創造する、データ・ドキュメントの活用を実現します。
まとめ
「ナレッジを機能的にまとめたい」——ほとんどすべての社会人に共通するニーズではないでしょうか。うまくナレッジをまとめるコツは、「見やすく・探しやすく・更新しやすい」ことに尽きます。ただ情報を集めただけでは、ナレッジはなかなか活用されません。だからこそ、目的や情報の基準を明確にして、誰でも使える形で整理しましょう。たとえば、社内Wiki、FAQ、ナレッジマネジメントツールといった選択肢の中から、自社の業務や文化に合った仕組みを見極めます。そのうえでルールやテンプレートを整えておくことで、情報が自然に蓄積・共有される環境ができます。検索しやすさや更新のしやすさの工夫も大切ですし、投稿しやすい空気づくりもナレッジ活用を加速させます。
sagurootはさまざまなファイルの一括検索と、部門ごとの絞り込みの両方の機能を備えて、組織・部門横断型と従来型の情報共有を同時に実現するナレッジマネジメントツール。さまざまな部門のスペシャリスト人材を知ることで、社内のコミュニケーションを活性化し、イノベーションを誘発します。