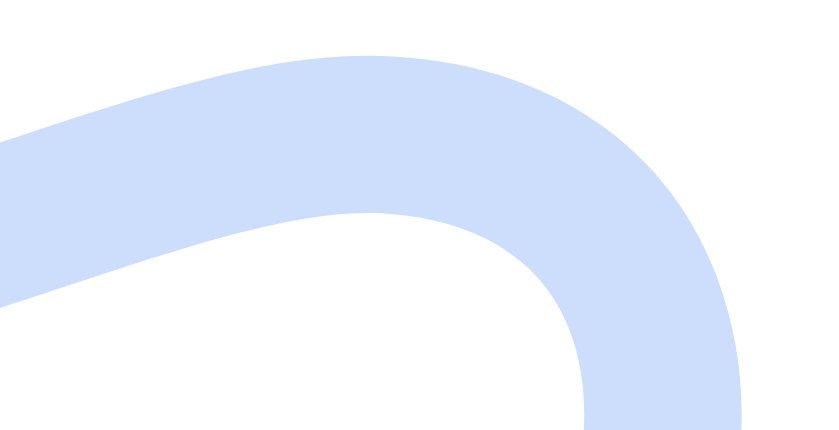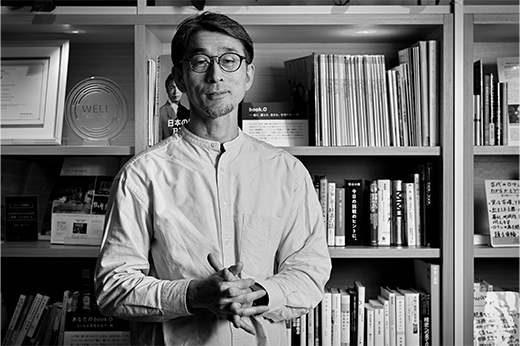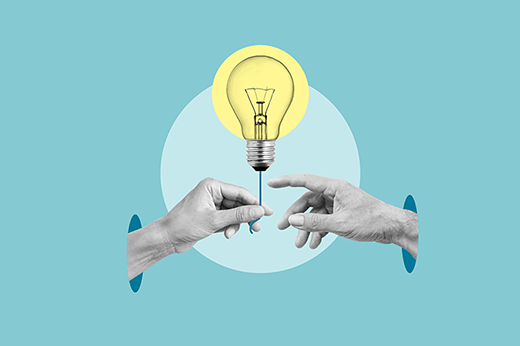社内wikiとは?失敗しないための対策やおすすめツールをご紹介
- 生産性向上

業務の効率化や情報共有の仕組みづくりに取り組む企業が増える中、「社内wiki」の導入が注目されています。社内wikiとは、ナレッジや業務マニュアル、社内ルールなどを集約し、組織内で共有・更新できる仕組みのこと。しかし、導入したものの結局は活用されなかったり、情報が乱立してかえって混乱を招いたりと、思うような成果が得られないケースも少なくありません。本コラムでは、社内wikiの基本から導入メリット、ツール選びのポイント、よくある失敗とその対策までを解説しますので、導入を検討中の方はぜひヒントにしてみてください。
社内wikiとは?

社内wikiとは、組織内の情報やノウハウ、業務マニュアルなどをチームで共有・蓄積するためのツールのこと。誰でも簡単に編集・更新ができるのが特徴で、属人化しやすい業務知識を組織全体の資産として残すことができます。基本機能としては、ページ作成・編集、コメント機能、バージョン管理、アクセス権限設定などがあり、チームの規模や目的に応じて柔軟に運用できます。必要な情報にすばやくアクセス可能なため、部署をまたいだ情報共有やナレッジマネジメントに役立ち、業務効率の向上や新人教育のスピードアップにも貢献します。近年、社内wikiは多くの企業で利用されています。
社内wikiを導入するメリット

なぜ多くの企業は社内wikiを導入しているのでしょうか。代表的なメリットを挙げてみました。
属人化の防止
社内wikiを導入することで、業務の属人化を防ぐことができます。特定の社員しか知らない業務内容や手順をwiki上に記録・共有することで、誰でも情報にアクセスできる状態になれば、担当者が不在でも業務が滞ることなく進められ、引き継ぎもスムーズに行えます。また、情報の透明化が進むことで、チーム全体の業務理解が深まり、組織全体の生産性や対応力の向上にもつながります。
社内ナレッジの一元管理
社内wikiは、点在しがちな情報やノウハウを一元的に管理するために有効なツールです。マニュアル、FAQ、会議の議事録、業務フローなど、日々蓄積されるさまざまな社内ナレッジを整理・保存することで、必要な情報にすぐアクセスできる環境を整えられるのがメリットです。検索性も高く、情報の更新や追記も容易なため、常に最新の知識をチームで共有が可能に。情報をまとめることで、業務効率の向上やナレッジの活用促進が期待できます。
情報共有のカルチャーづくり
社内wikiの運用を通じて、知っていることは共有するという意識が社内に根づきやすくなります。誰かが困ったときに助けになる情報を記録しておく習慣が生まれれば、チーム内の協力体制が強化され、業務の属人化を防ぐだけでなく、オープンで学び合える組織文化の醸成にもつながります。情報発信のハードルが低くなることで、日常的なナレッジ共有が活発になり、長期的には人材育成や組織力の底上げにも貢献します。
社内wikiツールの選び方のポイント

数あるツールの中から自社にふさわしいものを選ぶために、着目したいポイントを3点挙げました。
導入目的に合った機能があるか
まず重要なのは、自社の導入目的にマッチする機能を備えているかどうかです。例えば「業務マニュアルの一元管理」が目的であれば、階層構造でページを整理できるか、検索機能が充実しているか、更新履歴を追えるかなどがポイントになります。「ナレッジ共有の活性化」が主目的なら、コメント機能や「いいね」機能、ユーザー同士のコラボレーションを促す仕組みがあるかを確認しましょう。また他の業務ツールと連携できるかも、業務の効率性を左右する要素になります。
利用者にとって使いやすいか
社内wikiは継続的な更新と参照が求められるため、誰でも簡単に使えることが大切です。ページの作成・編集が直感的に行えるUIか、操作に迷ったときにヘルプがすぐ参照できるかなどをチェックしましょう。また、スマートフォンやタブレットにも対応しているか、社内外のどこからでもアクセスできるかなども実用性に大きく関わります。実際の利用シーンを想定しながら、「使い勝手」に注目することが導入を成功させるポイントです。
セキュリティ面は安全か
社内wikiには業務上の機密情報や個人情報が含まれることもあるため、セキュリティ面も見逃せません。ユーザーごとに閲覧・編集の権限を細かく設定できるか、不正アクセス対策が整っているかを確認しましょう。また、外部サービスとの連携時にも安全性が保たれるかどうかも重要なチェックポイントです。安心して運用を続けられる環境が整っているかどうかは、長期的な活用に直結します。
社内wiki導入でよくある失敗と対策

導入したものの活用しきれていない理由にはどのようなものがあるのでしょうか。
対策とともに見てみましょう。
社内wikiツールを使いこなせない
ツールの操作が複雑である、編集権限やフォルダ構成がわかりづらい、社員に対する十分な説明がない、といったことが原因として考えられます。対策としては、まず操作が直感的であるツールを選ぶこと。さらに導入初期にはトレーニングやマニュアルの整備を行い、社員が安心して利用できる環境を整えましょう。また、各部署に担当者をおいて運用体制を整えることも有効です。技術的な使い方だけでなく、「どんな情報を書けばよいか」「どのような書き方がよいか」といったガイドラインも整備すると、利用のハードルが下がります。
社内wikiが浸透していない
実際に使う社員が少なく、情報が更新されない状態に陥るのもよくある失敗です。そもそも使うメリットが社員に伝わっていない、情報が古いまま放置されて信頼を失っている、投稿が一部の人に偏っているなどの原因が見られます。担当者が率先して活用することで情報共有を進め、他社員にも「自分たちも使ってみよう」という流れを生みましょう。また、更新頻度の高いコンテンツを中心に整備し、「ここを見ればすぐに役立つ」という成功体験をユーザーに届けることも大切です。
社内wikiを考えている企業におすすめのツール

社内wikiを検討している、ナレッジを効果的に運用したい企業には、ナレッジマネジメントの定着を支援する仕組みが充実しているsagurootをおすすめします。sagurootは、直感的に使えるUI/UX設計で誰でも簡単に操作できること、タグやフォルダによる整理機能が優れているため、大量の情報も分類・検索しやすく、必要な情報にすばやくアクセスできることなどが特徴のナレッジマネジメントツール。KnowWhoの導入・構築により、専門的な知識やスキルを持つ社内人材を検索できるため、単なる情報共有にとどまらず、社内でのやりとりが活性化されやすいのもポイントです。
まとめ
情報を制する者は戦いを制す、という格言があります。これはビジネスや交渉など、あらゆる競争状況においても応用できる考え方。情報にあふれかえるこの時代、正確で多角的な情報をスピーディに集めて業務に反映させることは、ビジネスを加速させます。業務マニュアルやナレッジを一元管理し、組織全体で情報を共有・活用するための重要なツールとして、ぜひ戦略的に社内wikiを活用しましょう。sagurootは、検索体験を通じて価値ある情報を見出すとともに、ナレッジを持つ人材のネットワークを構築することで、企業の成長をサポートします。