運営の負荷を最小限に抑え、社内情報の検索性強化を実現

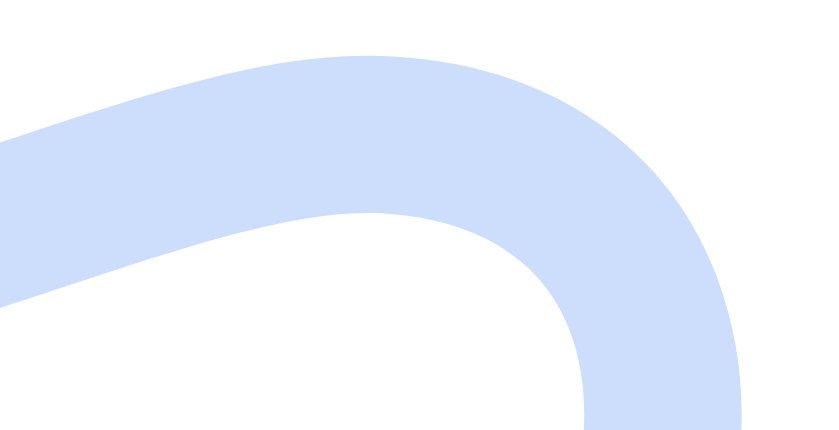
導入事例アサヒビール株式会社様 R&D部門
2024年よりR&D 部門を対象に「saguroot」を導入したアサヒビール株式会社。2025年からはグループ間のナレッジ共有としてアサヒグループジャパン内のグループ6社でのトライアルも開始する。本コラムでは、導入に至った背景から選定のポイント、実際に使ってみての効果など、ナレッジマネジメントを担当されているアサヒビール株式会社の木添博仁さんにお話を伺いました。


アサヒビール株式会社木添 博仁 氏
アサヒビール株式会社 イノベーション戦略部 副課長。2015年入社。ビールの技術開発と蒸留酒の商品開発に従事。2022年、現部署に異動、生成AI等を用いたR&Dの業務改善、環境に関連する技術開発企画、新価値創造に向けた会議体の運営、採用等に従事している。
sagurootを導入することになった背景を教えてください
研究開発を中心とした社内情報の検索性を高めたいと思ったからです。ある程度フォルダ構造を整えてはいたものの、無秩序に増えてしまう情報も多く、必要なデータにたどり着くまでに時間がかかるという課題がありました。また、「どのキーワードで検索すればヒットするのか分からない」という悩みも少なくありませんでした。最終的には、サイロ化※1した情報を改善し、イノベーションを生み出したいと思っています。人口が減少するなか、これまでと同じ方法ではビールをはじめとする飲料や食品の売上は下がっていくばかり…。だからこそ社内の技術知識をフル活用して、付加価値のある商品を開発することが必要だと考えています。
※1サイロ化:組織や情報が孤立し、共有できていない状態
数あるナレッジマネジメントツールの中から、sagurootに決められた理由は何でしょうか?
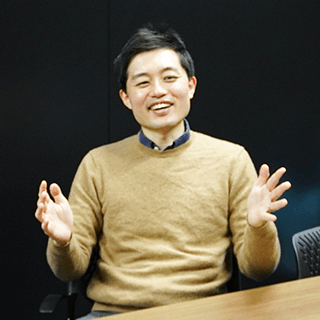
タグ機能は決め手のひとつです。検索性を高めるには、キーワードを知らない場合でも検索できるタグが必須だと考えています。一方で、ユーザー個々にタグ付けを任せると、タグが無秩序に増えすぎたり、逆に全く付与されないなど上手く機能しなくなることはわかっていたので、タグをどのようにするかは非常に悩ましいポイントでした。そこで、タグを適切に運用するツールとしてAIに注目していました。sagurootではAIドリブンなタグ設計で運営側の負荷を最小限に抑え、タグを適切に管理・運用できることが大きな魅力だと感じています。あとは、ChatGPTを使った要約機能を実装してもらえたのは大きかったです。検索した文書には、自動で生成された150-200文字程度の要約が出るのですが、技術文書は内容が複雑で1つ1つ読むには時間がかかるため、とても便利ですね。あとは、UIの使いやすさも魅力でした。見やすくて直感的に操作できることはもちろんですが、ユーザーが見たくなる、使いたくなるデザインも良かったです。
格納する情報はどのような方針で選択されたのでしょうか?
運用を始める前に各研究所のフォルダを確認して、メーカー資料、商品資料、提案資料、勉強資料など、役に立つものや知っていると楽しいものなど、約10,000点の資料を格納しました。トライアル、実証期間中には、現場のニーズを把握するためにヒアリングやアンケートも実施しました。技術情報は新しいモノだけが大事かといえばそんなことはなくて、技術者は現在の技術に至った背景や、歩んできた歴史を正しく理解することが求められます。過去にどんな検討がされ、選択され、どうやってここに行き着いたのか。過去を知らないと同じことを繰り返してしまうかもしれないので、一連の流れが大切。事業内容や部署の特性などを鑑みて、自社にふさわしい選択をする必要があると思います。
導入後の反応はいかがですか?
十分な人数が継続的に利用しており十分に活用されていると感じます。実際に社員からも「資料が見つけやすくなった」「UIが見やすい」などといった声が寄せられています。以前使用していた情報共有サービスでは、ひとつの資料を開くたびにバックボタンで戻る必要があり、地味ながらもストレスを感じるポイントでした。この点が改善されたのもメリットです。また、技術系の資料は同じ名称で複数回検討されていたりするため、中身を読まないとわからないことが多いので、生成AIを使った要約機能もとても好評です。
sagurootとBoxを連携されていますが、こちらの理由を教えてください
業務の手間を増やさずに、資料の充実を図ることが目的です。普段使用しているBoxに資料を保存するだけで、sagurootからも検索できるようになるため、利便性がさらに向上すると考えています。sagurootは、ピンポイントな検索ではなく、広く検索結果を提示してくれるので、新たな資料との出会いをもたらしてくれるんですね。例えば「糖質オフ」というキーワードを入れたとしても、「糖質オフだけでもこんなにあったんだ!」という驚きがありますし、学び直しのきっかけにもなります。今後、検索体験は、より充実したものになると思います。さらに、Boxはセキュリティ面で高い評価を得ており、その基準に準じた運用ができる点も、連携を決めた理由のひとつです。
丹青社の対応はいかがでしたか?
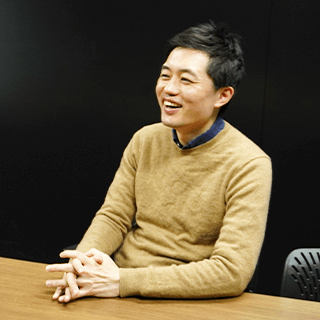
丹青社さんとは、協創/共創するためのコンソーシアム「point 0 marunouchi」でご一緒しています。sagurootの前身となるデモツールも試させていただき、その時点でUIの良さは実感していました。ただ、既存のツールと比較した際、社内導入の決め手としては少し弱いと感じていました。そこにChatGPT(Azure OpenAI)が入ってきたことが大きく、「これを活用すれば技術的にどんなことが可能なのか」を丹青社さんに相談させてもらいました。細かい要望を出すことも多かったのですが、一つひとつ誠実に対応してくださり、一緒に仕上げてきたという実感があります。丹青社さんはパートナーとして信頼できる存在だと思っています。
今後のsagurootには、どんなことを期待しますか?
現在はR&D部門で活用していますが、例えば将来的に営業部門にも展開するということを考えたら、チャット形式での対話機能があるといいかもしれません。自社の商品について、なぜ好まれているのか、どのような技術的背景があるのか、会社としてそこにどれほどのリソースをかけているのか、——これらを一本筋の通った形で自分の言葉で語れるようになるための学習ツールとして、チャット機能が活用できるのではないかと期待しています。また、今後グループ全体へ展開していく際には、より細かなセキュリティ階層の設定が可能になると、さらに安心して活用できると考えています。




